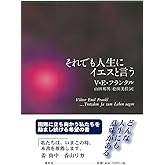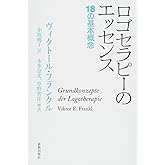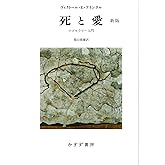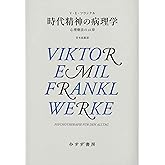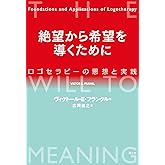本書はフランクル存命中に刊行された一巻選集である。フランクルの著作は膨大なものであり、ドイツ語でも英語でもその著作の全体を把握するのは容易ではない。フランクルの重要な著作でさえ、オリジナルの言語では手に入れにくい状態が見受けられる。私たちはともすれば当たり前に受け止めてしまうかも知れないが、日本で二つの出版社から著作集が組まれて容易に手にできるということ自体が特別なことと言えよう。本書のまえがきにおけるフランクルのホーボーゲン番号が必要かもしれないという指摘は誇張ではないのである。
フランクルが存命中に刊行された本書からは、フランクルがどのように受け止められ、何を読者に伝えたいのかが如実に伝わってくる。それはフランクルその人の魅力である。クロイツァーによるまえがき、講演録、学術論文、自伝的内容を含む新聞記事、そして監訳者による解説で構成される本書は、単著として別に刊行される講演録や自伝に含まれる内容を盛り込んだ重要著作何冊分もが一冊にまとめられたものと言えよう。第二次大戦前の論文や新聞記事までをも含む本書は、フランクル自身が自らを、あるいは当時の人々がフランクルを、どのように位置づけていたかを正確に伝えてくれるものである。
フランクルは数多くの講演を残し、日本語訳で読める翻訳の大半がそうであると言ってもよい。フランクルの英文著作を紐解くと、学問的な文章であるにも関わらず、深く揺さぶられる。後に『それでも人生にイエスと言う』として刊行され、『識られざる神』にも再録される名講演が本書には含まれている。赤坂桃子氏の翻訳はちょうど英文著作を紐解くときに感じるようなフランクルの息遣いを再現するものであり、本文に挿し込まれた訳注はフランクルが意図する言い回しを正確に読者に伝えようとする配慮に満ちている。全編を貫くフランクルの律動を伝える翻訳は読者にフランクルとの出会いをもたらすものであろう。
残念ながら原著に含まれていた文献表は割愛されているが、その向きには解説でも言及されるバティアーニの仕事(没後論文集『虚無感について』の解説など)を参照してもらえれば良いと思う。割愛された文献リストの代わりに付された監訳者による解説は、今フランクルの思想がどのような可能性を持っているのかを現代の精神療法に照らして問いかけるものである。精神療法は刻々と変化している。臨床の現場にあってフランクルがどのような問いと向き合いその思想を深めていったのかをうかがわせる本書は、その核となるものを明らかにし、フランクルその人と出会わせてくれる類まれな一冊である。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

精神療法における意味の問題: ロゴセラピー 魂の癒し 単行本 – 2016/10/26
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
生き方を考える哲学と,精神医学的治療手法の融和を成し遂げたロゴ(意味)セラピー。しかし,その意義について実践可能な形での紹介は未だ不十分な状況である。
本書では,「複層的なフランクル像」を求めて,成立史的な面で対照的な二つの大学講義(1977年のザルツブルク大学週間での連続講義と1946年の市民大学での講演),寄稿論文として書かれた「自伝的素描」(1982年),晩年の特別講演(1988年),S.フロイト没後25年にあたってフランクルが寄せた新聞記事(1964年)を収載。
なお,第1章「精神療法における意味の問題」(1977年)は本邦初訳。また,第2章「人生の意味と価値について」(1946年)は,できるだけ原文に忠実な形で訳出を心掛け,『それでも人生にイエスと言う』(春秋社)の新訳の試みでもある(*ただし今回翻訳権を取得した原書の編集では,講演の一部がカットされている)。
さらには,監訳者による解説――ロゴセラピーの治療の特徴,フランクル独自の精神医学用語,DSMとの診断基準比較等について――を付し,日本の精神医学の臨床現場における実践的理解を図る。
本書では,「複層的なフランクル像」を求めて,成立史的な面で対照的な二つの大学講義(1977年のザルツブルク大学週間での連続講義と1946年の市民大学での講演),寄稿論文として書かれた「自伝的素描」(1982年),晩年の特別講演(1988年),S.フロイト没後25年にあたってフランクルが寄せた新聞記事(1964年)を収載。
なお,第1章「精神療法における意味の問題」(1977年)は本邦初訳。また,第2章「人生の意味と価値について」(1946年)は,できるだけ原文に忠実な形で訳出を心掛け,『それでも人生にイエスと言う』(春秋社)の新訳の試みでもある(*ただし今回翻訳権を取得した原書の編集では,講演の一部がカットされている)。
さらには,監訳者による解説――ロゴセラピーの治療の特徴,フランクル独自の精神医学用語,DSMとの診断基準比較等について――を付し,日本の精神医学の臨床現場における実践的理解を図る。
- 本の長さ276ページ
- 言語日本語
- 出版社北大路書房
- 発売日2016/10/26
- 寸法13.4 x 2 x 19.5 cm
- ISBN-104762829463
- ISBN-13978-4762829468
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
商品の説明
著者について
ヴィクトール・E・フランクル[Viktor E. Frankl]はウィーン大学の神経学および精神医学の教授であり,同時に25年間にわたってウィーン市立病院神経科科長を務めた。彼が創始した「ロゴセラピー/実存分析」は,「精神療法の第三ウィーン学派」とも称される。ハーバード大学ならびに,スタンフォード,ダラス,ピッツバーグの各大学で客員教授として教鞭をとり,カリフォルニア州サンディエゴにあるアメリカ合衆国国際大学のロゴセラピー講座のディスティングイッシュト・プロフェッサー(注:Distinguished Professorは,日本語の名誉教授,特別栄誉教授に似ているが,厳密にはそのどちらの概念にも当てはまらない)でもあった。
フランクルは1905年にウィーンに生まれた。ウィーン大学で医学博士号を取得し,のちに哲学博士号も取得した。第二次世界大戦中は,3年間にわたってアウシュヴィッツ,ダッハウ,その他の強制収容所での生活を経験した。
フランクルは40年もの間,世界を股にかけて数え切れないほどの講演旅行に出た。ヨーロッパ,北アメリカおよび南アメリカ,アジア,アフリカで二十…
寺田 浩(てらだ ひろし)
医療法人社団 明光会 こころとからだのクリニック あおいクリニック理事長,医師,医学博士,精神保健指定医,日本精神神経学会専門医,日本医師会認定産業医。
静岡県生まれ。
1993年聖マリアンナ医科大学医学部卒業。JR東京総合病院で臨床研修後,浜松医科大学精神科医局に入局し,当時の教授である大原健士郎先生に出会う。その後横浜相原病院においても勤務を共にし,10年以上にわたり大原先生から森田療法など,師事。その後現職に至る。2014年千葉大学大学院医学薬学府応用精神医療学修了。
現在,臨床に従事する傍ら,光トポグラフィを用いたうつ病・発達障害などの精神疾患の診断と治療効果の評価への応用や,ショートケアにおける様々な精神療法の集団への実践など,新たな精神医学的手法の可能性を追求する研究も併せて行っている。
[主な著書や論文]
『ショートケアとリワークの実践ガイド』(編著) 北大路書房 2014。
「精神科医療におけるリワークを考える」 新薬と臨床,62(9),1505-1513,2013。
など多数
寺田 治子(てらだ・はるこ)
医療法人社団 明光会 こころとからだのクリニック あおいクリニック院長,医師,精神保健指定医,日本精神神経学会専門医,日本医師会認定産業医。
埼玉県生まれ。
順天堂大学医学部卒業後,順天堂大学,東邦大学大森病院心療内科にて研修。
[主な著書]
『ショートケアとリワークの実践ガイド』,北大路書房,2014。
など
赤坂 桃子(あかさか・ももこ)
翻訳家。東京都出身。上智大学文学部ドイツ文学科および慶應大学文学部卒業。
実務翻訳・通訳を経て,現在は出版翻訳を中心に活動している。
日本ロゴセラピーゼミナールにて,南ドイツ・ロゴセラピー研究所公認ロゴセラピスト勝田茅生氏のもとでロゴセラピーを学ぶ。ヴィクトール・フランクルの伝記(ハドン・クリングバーグ・ジュニア著。下記参照)の翻訳,ウィーンのヴィクトール・フランクル研究所所長アレクサンダー・バティアーニ教授の日本における学会講演の通訳なども行っている。
[主な翻訳書]
ヴィクトール・E・フランクル著,赤坂桃子訳『ロゴセラピーのエッセンス 18の基本概念』新教出版社,2016。
トム・ヒレンブラント著,赤坂桃子訳『ドローンランド』河出書房新社,2016。
メヒティルト・ボルマン著,赤坂桃子訳『希望のかたわれ』河出書房新社,2015。
メヒティルト・ボルマン著,赤坂桃子訳『沈黙を破る者』河出書房新社,2014。
イレーネ・ディーシェ著,赤坂桃子訳『お父さんの手紙』新教出版社,2014…
フランクルは1905年にウィーンに生まれた。ウィーン大学で医学博士号を取得し,のちに哲学博士号も取得した。第二次世界大戦中は,3年間にわたってアウシュヴィッツ,ダッハウ,その他の強制収容所での生活を経験した。
フランクルは40年もの間,世界を股にかけて数え切れないほどの講演旅行に出た。ヨーロッパ,北アメリカおよび南アメリカ,アジア,アフリカで二十…
寺田 浩(てらだ ひろし)
医療法人社団 明光会 こころとからだのクリニック あおいクリニック理事長,医師,医学博士,精神保健指定医,日本精神神経学会専門医,日本医師会認定産業医。
静岡県生まれ。
1993年聖マリアンナ医科大学医学部卒業。JR東京総合病院で臨床研修後,浜松医科大学精神科医局に入局し,当時の教授である大原健士郎先生に出会う。その後横浜相原病院においても勤務を共にし,10年以上にわたり大原先生から森田療法など,師事。その後現職に至る。2014年千葉大学大学院医学薬学府応用精神医療学修了。
現在,臨床に従事する傍ら,光トポグラフィを用いたうつ病・発達障害などの精神疾患の診断と治療効果の評価への応用や,ショートケアにおける様々な精神療法の集団への実践など,新たな精神医学的手法の可能性を追求する研究も併せて行っている。
[主な著書や論文]
『ショートケアとリワークの実践ガイド』(編著) 北大路書房 2014。
「精神科医療におけるリワークを考える」 新薬と臨床,62(9),1505-1513,2013。
など多数
寺田 治子(てらだ・はるこ)
医療法人社団 明光会 こころとからだのクリニック あおいクリニック院長,医師,精神保健指定医,日本精神神経学会専門医,日本医師会認定産業医。
埼玉県生まれ。
順天堂大学医学部卒業後,順天堂大学,東邦大学大森病院心療内科にて研修。
[主な著書]
『ショートケアとリワークの実践ガイド』,北大路書房,2014。
など
赤坂 桃子(あかさか・ももこ)
翻訳家。東京都出身。上智大学文学部ドイツ文学科および慶應大学文学部卒業。
実務翻訳・通訳を経て,現在は出版翻訳を中心に活動している。
日本ロゴセラピーゼミナールにて,南ドイツ・ロゴセラピー研究所公認ロゴセラピスト勝田茅生氏のもとでロゴセラピーを学ぶ。ヴィクトール・フランクルの伝記(ハドン・クリングバーグ・ジュニア著。下記参照)の翻訳,ウィーンのヴィクトール・フランクル研究所所長アレクサンダー・バティアーニ教授の日本における学会講演の通訳なども行っている。
[主な翻訳書]
ヴィクトール・E・フランクル著,赤坂桃子訳『ロゴセラピーのエッセンス 18の基本概念』新教出版社,2016。
トム・ヒレンブラント著,赤坂桃子訳『ドローンランド』河出書房新社,2016。
メヒティルト・ボルマン著,赤坂桃子訳『希望のかたわれ』河出書房新社,2015。
メヒティルト・ボルマン著,赤坂桃子訳『沈黙を破る者』河出書房新社,2014。
イレーネ・ディーシェ著,赤坂桃子訳『お父さんの手紙』新教出版社,2014…
登録情報
- 出版社 : 北大路書房 (2016/10/26)
- 発売日 : 2016/10/26
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 276ページ
- ISBN-10 : 4762829463
- ISBN-13 : 978-4762829468
- 寸法 : 13.4 x 2 x 19.5 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 542,896位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 19,097位心理学 (本)
- カスタマーレビュー:
カスタマーレビュー
星5つ中4.7つ
5つのうち4.7つ
4グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ66%34%0%0%0%66%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ66%34%0%0%0%34%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ66%34%0%0%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ66%34%0%0%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ66%34%0%0%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2016年11月5日に日本でレビュー済みAmazonで購入「人生が自分に何を期待しているのか?」ロゴセラピーを意味による癒しと捉えるならば、様々な事柄に対して奉仕・没頭することが、意味の実現に結び付く。本著は、精神療法だけでなく、人生訓としても意味のある内容だと感じた。
- 2016年11月2日に日本でレビュー済みAmazonで購入前半はフランクルの講義録ということもあり、臨場感ある内容となっている。用語の解説もあり、非常に読み応えがある。後半にはロゴセラピーを臨床応用する上で参考になるエッセンスが詰まっている。身体因、心因、精神因に関するフランクルの病因論は非常に興味深い内容であった。