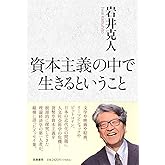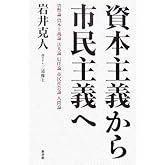著者が経済学を学び研究者となっていく人生遍歴に沿って、多くの経済学者たちと理論名や要点が列挙される。経済学に明るい人には興味関心が惹きつけられるであろう。
個人的には経済学を知らないが、本書では、例えば、リンゴを多く食べるか、ナシを多く食べるかという消費における選択問題について、リンゴの生産量と消費量を一致させ、かつナシの生産量と消費量を一致させる均衡状態を実現させるためにどう解くか、というのが経済問題になるとのこと。それを解いて、数式が見た目も美しい解であればエレガントと悦に入ったりするのだろうか。
読み進めると、著者が、長年の論争や対立すると考えられてきた理論について、膨大な文献渉猟と読解の上に丁寧に解きほぐしつつ盲点になっていた本質を見抜いて、両者を統一する理論を構築したり、一区切りすると新たに湧いて来た疑問について、経済学に限らず、文学、法学、哲学等、疑問を解明するために必要な他領域についても膨大な文献渉猟と読解を行い、新たな視点を導入して理論構築して研究されて来たことが、言わば追体験できるような面白さ、久々に読書の喜びを感じられた。超オススメです。
以下、個人的な考え。
マルクスは、なぜ価値形態論を考えたのか。「資本論」は貨幣ありきから始めてもいいように思われるが、マルクスは、なぜ「資本論」の冒頭に価値形態論を書いたのか。その積年の疑問についての答えは、本書には無かった。
最近、40年経過して文庫出版された、浅田彰氏著「構造と力」について私はAmazonレビューで、マルクスは、物とは全く異なる貨幣の特異性を、ヘーゲルの弁証法である正・反・合では説明し尽くせないため価値形態論で捉えることを考えた、マルクスは価値形態論によってヘーゲルの弁証法を乗り越えた、その価値形態論によって資本制社会をクラインの壷で表現したのは浅田氏の慧眼である、と書いた。
それ以前に、柄谷行人氏は「マルクスその可能性の中心」で価値形態論に着目した。主要著作が英文出版され、もしかするとノーベル文学賞候補に柄谷氏が入ってもおかしくないと思い、おそらくマルクス主義者と見なされて入らないだろうとも思った(交換様式Dが今後どう描かれるかわからないが、今のところ交換様式論はマルクスの補完に感じる。「力と交換様式」についての私のAmazonレビュー)が、バーグルエン哲学・文化賞を受賞された。
本書「経済学の宇宙」を読むと、私は経済学に明るくないが、岩井克人氏こそノーベル賞にふさわしいのではないかと思えてくる。
著者は、マルクスの価値形態論によって、マルクスが準拠した労働価値説は破綻する、とする。
なぜならば、貨幣形態は、一般的な価値形態から全体的な価値形態へ逆転する、逆転した際、貨幣の貨幣としての価値は物としての価値を上回っている、故に貨幣の価値は物の価値に還元できないから、という証明。
例えて言えば、動物というカテゴリーには、ライオン、ウマ、イヌなどがいるが、そのカテゴリーの中に、ライオンの隣に動物がいる状態。その動物はライオン以上の種類のウマ、イヌなどを含むので、価値が上回っている、という感じだろうか。
著者は、価値形態論によって労働価値説は破綻する、と。もしかすると、そのことにマルクスは気づいたからお茶を濁し、「資本論」の冒頭だけで価値形態論を早々に切り上げたのかもしれない。
労働価値説が破綻すれば、労働価値説を土台とする搾取論も破綻する。労働者よ、立ち上がれ、は腰砕けになりかねない。
労働が生産する商品やサービスの価値は、投入された労働だけで決まるものではない。例えば、機械が商品やサービスを生産する場合、機械を作るのに投入された労働の価値が、生産された商品やサービスの価値を決めるのではない。機械を生産した労働の価値、機械の購入額の減価償却、商品やサービスの価格、それらは別である。
究極は、労働価値を測る、つまり測るための労働価値の単位を決めることが不可能であることが、労働価値説が成立しない理由である。労働価値説の破綻は、マルクスの価値形態論には関係ないのではなかろうか。
労働価値説に基づく、マルクスの搾取論は、階級闘争として政治的に利用されて来た。が、労働価値説が破綻しているので、労働価値説をベースとする搾取論も破綻している。
搾取論は、ある局面では妥当する(共産主義革命は貧しかった国々、貧富の差が著しかった国々で起きた)。然し乍ら、ある商品やサービスが圧倒的な利益をもたらし、労働者への分配も給与相場を相当超えていれば、労働者は搾取されているとは感じない局面もある。つまり、労働価値の単位を決めることが不可能なので、搾取論も成り立たない。個人による労働と協業による労働の区分けは考え方としては分かるが、労働価値を測る絶対的な単位はないので、その区分けは明示できない。統計データとして変動する給与相場、物価相場があるだけである。
労働に価値はあるが、それだけが資本が利益を得る差異ではない。本書にあるように、産業資本主義は、工場生産だけではなく、農村からの労働者が農村での賃金以上を求めなかった(搾取されていると感じなかった)ことからも利益を得ていた。
資本論でマルクスが価値形態論を、物ではなく商品、商品の集積から始めた理由が分かったような気がする。それは、マルクスが労働価値説をとるからである。
労働価値説では、商品の価値は、その商品に投入された人間の労働価値である。物、例えば自然物、道端に転がっている石は労働力が投入されていないので商品ではない。その石が貴重な物であっても、労働力が投入されていないので商品ではない。
人間の労働が投入されていない物は、商品ではないとマルクスは考えたのではなかろうか。しかし、貴重な石も、売りと買いの出会うマーケットで「欲求の二重の一致」に出会う商品にならないとも限らない。
マルクスの価値形態論で交換を表すイコールは、本書で著者が対比する「脳」とは異なる「間」である。例えば、Aさんという人と、Bさんという人の「間」で起きる交換である。
だが、それだけでは「自己循環論法」を表せない。
Aさん視点で見ると、Aさんは、今まで自分に蓄積されてきた情報と、外から、つまりBさんからもたらされた情報を、瞬時に照合(交換)し、同じか異なるか、全く異なるか、少し異なるかを、瞬時に判断している。(価値には差異しかない:ソシュール)
脳が認識する際に常に、マルクスの価値形態論が作動している。Aさんは、蓄積されてきた情報(相対的な価値形態)と外からもたらされた情報(等価形態)を照合し、頭の中で、単純な価値形態なのか、全体的な価値形態なのか、一般的価値形態なのかが作動する。Aさんは、社会のあらゆる価値を、そのようにして身につける。そこにおいて、自己循環論法が成立するのではなかろうか。今という瞬間、この文を読んでいるまさに今、起きていることではなかろうか。
マルクスの価値形態論での交換とは、コミュニケーションのことであり、マルクスの言う交通である。
コミュニケーションは、対人関係だけで起こるものではなく、対人も含め外界に対する活動全てのことである。
一般的価値形態から全体的価値形態へ逆転、さらに逆転を繰り返し、あらゆる差異から利益を獲得し続けて爆進する資本主義は、マルクスの価値形態、換言すれば交通、人間のコミュニケーションに適合するために、大恐慌やハイパーインフレを突き抜ける不均衡(破壊してしまうと、もはや不均衡とは呼べないが)が生じない限り無くなることはない。言語、法、貨幣のみならず、あらゆる一般的価値は、人間のコミュニケーションに適合するが故に、適者生存してきた。
人は、身につけた社会のあらゆる価値から、自らの言動を行うが、その際、複数ある価値の中から、どの価値を優先するかで、その人の言動が左右される。人を殺してはいけない、法律にも倫理にも反すると分かっていても、条理によって兄が弟を殺したのは「高瀬舟」。
人の頭(心、精神と言ってもいいが)にあると思ってしまう、エス・自我・超自我のうち、超自我とされるものは、ひとつと言っても複数あると言ってもいいが、いずれにせよ、人が身につけた社会のあらゆる価値が頭で相剋して、人の言動に影響を与える。人は言動の結果から、ある価値が優先されたに違いないと推理するだけである。超自我なるものは、人の頭の中に固着するが、コミュニケーションによって常に外部とつながっている。
著者は「言語・法・貨幣」を取り上げる。かつて柄谷行人氏は「言語・数・貨幣」を取り上げた。テルケル派も同様だったか。その違いも気になるが、著者が終わりに提示した「市民社会論」は、柄谷行人氏の「交換様式D」と通じる何かがあるように感じた。
柄谷氏は交換様式Dは「宗教」として向こうから来るとするが、自由と平等に反する恣意性だらけの宗教には全く賛成できないし感心しない。
著者の掲げる「法」。これからの世界、様々な地域で異なった、多数の社会から成る世界にとって、「法」こそ自由と平等を普遍的に実現していくために最重要になると個人的に思っており、著者の考えに大賛成である。著者のその後の論考が非常に楽しみである。
この注文でお急ぎ便、お届け日時指定便を無料体験
Amazonプライム無料体験について
Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

経済学の宇宙 単行本 – 2015/4/1
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥3,080","priceAmount":3080.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"3,080","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"29x9fc%2FDlROuDN1I2JuaC5Ls62UM%2FYUQGTnZekVakk8gRtYsCACAkypwwd%2FB7qzYKUmyhOZQCOELQyB%2FRuTHOob2AOM9TrfYBPofUU%2FP%2FDBx7QupEzysBrcfJqVFcnW9hghB8oaUhrE%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}, {"displayPrice":"¥392","priceAmount":392.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"392","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"29x9fc%2FDlROuDN1I2JuaC5Ls62UM%2FYUQk%2FjU7ChCSB5Ks7f0YajsFYGnBPFU4rru8VP1JkhpPjDQz0xQTEQiMQ3uomkyZiwwaK%2FBnHaabvH5F4UgWsTIIAglSbU7TU%2BLj2IVK4WMxSokH2nqDhp3LpY8S3IX9oZCs4uwAGoNp8KtafaxsonlqA%3D%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"USED","aapiBuyingOptionIndex":1}]}
購入オプションとあわせ買い
●日本経済新聞社発表「2015年エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10」第1位
「自らの知的内面の葛藤の軌跡を、見事に浮き彫りにしている。現在の経済学や企業のありかたへの警鐘ともなっている」(清家篤・慶応義塾長)--。経済学者の知的格闘の軌跡を超えた、現代経済の地殻変動を読み解くうえでの必読の書だ。
●経済を考え抜いた格闘の軌跡
「学問をする人間としては幸せでしたが、学者としては成功したと思っていない――」(岩井克人)。
本書は、「不均衡動学」「資本主義論」「貨幣論」「法人論」「貨幣・法・言語論」などで、経済を多角的にとらえてきた岩井克人が、その遍歴と心情を初めて明らかにする知的興奮の書。
マルクスに感銘を受けて経済学部へ進学した青年が、小宮隆太郎、宇沢弘文と出会い近代経済学に目覚める。そして、MITへ留学し、サムエルソン、ソロー、トービンなど経済学の巨人たちから教えを受け、経済学の頂点を目指す。だが、新古典派からケインズに軸を移すことによって、学者としては世界の潮流から離れることになった……。岩井氏の軌跡は挫折と苦悩に満ちたものであった
●知の巨人たちの知られざる素顔
本書を通読すると、岩井理論に加え、様々な経済学説のエッセンスを吸収できる。さらに、経済学に脳科学の成果を取り込もうとする最近の経済学界の動きや、『21世紀の資本』が世界でベストセラーとなっているトマ・ピケティ氏の研究などへの言及もあり、最先端とされる研究分野を評価する座標軸を手にできる。
また、岩井氏が接してきた知識人たちの群像も楽しめる。▽(米国で多くの接点を持った経済学者=いずれもノーベル経済学賞を受賞)サムエルソン、ソロー、トービン、クープマンス、モディリアーニ、アカロフ、スティグリッツ、マートン、ダイアモンド……▽(東京大学などで交流を深めた日本の経済学者)宇沢弘文、小宮隆太郎、根岸隆、浜田宏一、青木昌彦、猪木武徳、石川経夫、奥野正寛、吉川洋……▽(エール大学や、「ニューアカデミズム」ブームの母体となった「ゼロの会」などで親しくなった文化人)加藤周一、武満徹、柄谷行人、三浦雅士、中沢新一、浅田彰、山口昌男。彼らは岩井氏にどんな影響を与えてきたのか、興味深いエピソードが満載の書でもある。
「自らの知的内面の葛藤の軌跡を、見事に浮き彫りにしている。現在の経済学や企業のありかたへの警鐘ともなっている」(清家篤・慶応義塾長)--。経済学者の知的格闘の軌跡を超えた、現代経済の地殻変動を読み解くうえでの必読の書だ。
●経済を考え抜いた格闘の軌跡
「学問をする人間としては幸せでしたが、学者としては成功したと思っていない――」(岩井克人)。
本書は、「不均衡動学」「資本主義論」「貨幣論」「法人論」「貨幣・法・言語論」などで、経済を多角的にとらえてきた岩井克人が、その遍歴と心情を初めて明らかにする知的興奮の書。
マルクスに感銘を受けて経済学部へ進学した青年が、小宮隆太郎、宇沢弘文と出会い近代経済学に目覚める。そして、MITへ留学し、サムエルソン、ソロー、トービンなど経済学の巨人たちから教えを受け、経済学の頂点を目指す。だが、新古典派からケインズに軸を移すことによって、学者としては世界の潮流から離れることになった……。岩井氏の軌跡は挫折と苦悩に満ちたものであった
●知の巨人たちの知られざる素顔
本書を通読すると、岩井理論に加え、様々な経済学説のエッセンスを吸収できる。さらに、経済学に脳科学の成果を取り込もうとする最近の経済学界の動きや、『21世紀の資本』が世界でベストセラーとなっているトマ・ピケティ氏の研究などへの言及もあり、最先端とされる研究分野を評価する座標軸を手にできる。
また、岩井氏が接してきた知識人たちの群像も楽しめる。▽(米国で多くの接点を持った経済学者=いずれもノーベル経済学賞を受賞)サムエルソン、ソロー、トービン、クープマンス、モディリアーニ、アカロフ、スティグリッツ、マートン、ダイアモンド……▽(東京大学などで交流を深めた日本の経済学者)宇沢弘文、小宮隆太郎、根岸隆、浜田宏一、青木昌彦、猪木武徳、石川経夫、奥野正寛、吉川洋……▽(エール大学や、「ニューアカデミズム」ブームの母体となった「ゼロの会」などで親しくなった文化人)加藤周一、武満徹、柄谷行人、三浦雅士、中沢新一、浅田彰、山口昌男。彼らは岩井氏にどんな影響を与えてきたのか、興味深いエピソードが満載の書でもある。
- 本の長さ490ページ
- 言語日本語
- 出版社日経BPマーケティング(日本経済新聞出版
- 発売日2015/4/1
- 寸法14.5 x 3.3 x 19.6 cm
- ISBN-104532356423
- ISBN-13978-4532356422
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
商品の説明
著者について
岩井 克人(いわい・かつひと)
1969年東京大学経済学部卒、72年マサチューセッツ工科大学(MIT)Ph.D.取得。73年エール大学助教授、79年エール大学コウルズ経済研究所上級研究員、81年東京大学助教授、88年ペンシルベニア大学客員教授・プリンストン大学客員准教授、89年東京大学教授、2010年定年退職。現在、国際基督教大学客員教授、東京財団名誉研究員、東京大学名誉教授。主な著書に『Disequilibrium Dynamics(不均衡動学)』(日経・経済図書文化賞特賞)『ヴェニスの商人の資本論』『貨幣論』(サントリー学芸賞)『二十一世紀の資本主義論』『会社はこれからどうなるのか』(小林秀雄賞)、共著に『M&A国富論』(M&Aフォーラム賞正賞)ほか。
聞き手 前田 裕之(まえだ・ひろゆき)
1986年東京大学経済学部卒、日本経済新聞社入社。現在、編集局経済解説部編集委員。主な著書に『激震 関西金融』『地域からの金融革命』『脱「常識」の銀行経営』、共著に『松下 復活への賭け』『アベノミクスを考える(電子書籍)』、論文に「経済危機における日本人の意識と行動」ほか。
1969年東京大学経済学部卒、72年マサチューセッツ工科大学(MIT)Ph.D.取得。73年エール大学助教授、79年エール大学コウルズ経済研究所上級研究員、81年東京大学助教授、88年ペンシルベニア大学客員教授・プリンストン大学客員准教授、89年東京大学教授、2010年定年退職。現在、国際基督教大学客員教授、東京財団名誉研究員、東京大学名誉教授。主な著書に『Disequilibrium Dynamics(不均衡動学)』(日経・経済図書文化賞特賞)『ヴェニスの商人の資本論』『貨幣論』(サントリー学芸賞)『二十一世紀の資本主義論』『会社はこれからどうなるのか』(小林秀雄賞)、共著に『M&A国富論』(M&Aフォーラム賞正賞)ほか。
聞き手 前田 裕之(まえだ・ひろゆき)
1986年東京大学経済学部卒、日本経済新聞社入社。現在、編集局経済解説部編集委員。主な著書に『激震 関西金融』『地域からの金融革命』『脱「常識」の銀行経営』、共著に『松下 復活への賭け』『アベノミクスを考える(電子書籍)』、論文に「経済危機における日本人の意識と行動」ほか。
登録情報
- 出版社 : 日経BPマーケティング(日本経済新聞出版; New版 (2015/4/1)
- 発売日 : 2015/4/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 490ページ
- ISBN-10 : 4532356423
- ISBN-13 : 978-4532356422
- 寸法 : 14.5 x 3.3 x 19.6 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 250,409位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 164位マクロ経済学 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.4つ
5つのうち4.4つ
67グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2024年1月19日に日本でレビュー済みAmazonで購入
- 2024年11月30日に日本でレビュー済み名前だけは知っていた岩井克人の長い学問的自伝。経済学者の自伝としては森嶋通夫のそれもめっぽう面白いがこちらもそれに劣らぬ面白さ。経済学に進むきっかけから偶然と必然が絡み合って自分のオリジナル理論(不均衡動学)を形成し、それゆえに世界の(つまり英米の)経済学の主流から外れ、それでも自分なりの思索を推し進めてゆく。理論自体が提起する問題(内生的問題?)と生活やらの諸々から生起する外生的問題の絡み合いの中から次々と新しい理論的成果を生んでゆく姿には興奮間違いなし。
注の専門的解説は分からないので読み飛ばしたがそれでも十分面白い。傑作じゃないか?
こういうのを若いとき読んだら数理経済学者を目指したろうなあ。
[補足というか蛇足]
ついでにいうと、森嶋(「マルクスの経済学」を書いた)、宇沢弘文(もと共産党シンパでなんと不破元委員長と一緒に経済学の勉強をしたこともあったらしい)、この人と、マルクスが日本の「近代経済学」(死語だけど)の数理経済学者に与えた影響の大きさよ。
関係ないけど、小室直樹がMITに留学してた時、サミュエルソンが授業で、この論文のこの部分の数学的誤りはモリシマの指摘で訂正した、的な話をしていてとても誇らしかった、てな話を思い出した。
あ、もひとつついでにいうと、この本を読みながら、竹中平蔵さんについて書かれた「市場と権力」を思い出した。同じ「経済学者」と名前がついてもこうも違うのかね、って。ま、あちらは竹中嫌いが書いた本だからって事情は割り引くにしてもね。
若い人は竹中平蔵(社会的には成功者だけど)を目指すんじゃなくて、この人や宇沢や森嶋みたいな学者を目指してほしいなあ。
- 2020年4月18日に日本でレビュー済みAmazonで購入井上靖のしろばんばを読んだ感じと似たノスタルジックな満足感がある。経済学の話は崇高にレベルが高く、ストイックだけど、論文じゃないから、もう少し砕いて欲しかった。
- 2023年11月23日に日本でレビュー済みAmazonで購入率直に語られているので、著者の人柄もよくわかり、読み応えがある。
- 2023年1月24日に日本でレビュー済みAmazonで購入内容は最高に面白い☆☆☆☆☆
こんな形式で電子書籍にする意味あるのか?☆
- 2024年9月4日に日本でレビュー済みかつて留学でP・サミュエルソンを始めとする米主流経済学コミュニティに椅子を得た著者。
その後自らの信条でそこから逸れていったことに、悔恨が見え隠れしつつ気概も感じさせる。
そのあたりの諦念も幾分混じった微妙なニュアンスが、リアリティを感じさせ引き込まれた。
とはいえ80年代から十数年は日本では経済学界のピラミッドの頂点に近い集団内にいた人物。
その人生譚をその時々に向き合った経済理論を交えて語ってくれることが面白くないはずはない。
経済学が特定の仮定群でもって雑多な現実を捨象していく以上、議論が絶えることはないだろう。
- 2020年5月6日に日本でレビュー済みAmazonで購入2015年11月に読了した本。文句なしに、2015年に読んだベストな本だったと記憶している。
特にマクロ経済学を中級程度までかじった人には、この恐ろしく博識な経済学者の倫理観、使命、葛藤、着目点、思索の軌跡が存分に楽しめ、同時に先生の物事への真摯な向き合い方が非常に心に沁みるものがある。
マクロ経済は短期のみならず長期でも完全雇用以下のレベルで暫定的に漂流している(「均衡している」)場合が多いというのはケインズ経済学が示したことだが、ヴィクセルとケインズを繋ぎ合わせて、この経済の調整過程を「不均衡動学モデル(Disequilibrium Dynamics)」として示し、次に貨幣の役割については、マルクス資本論の根幹をなす価値形態説には、そもそも貨幣の定義上の間違いがある為に、そのことがマルクス経済学の理論を崩壊させていると論理的に指摘するなど、諸経済学者の理論・言説を非常に丹念に読み込み、止揚させて新たな理論を構築していく類稀なる知力に畏怖の念を抱き、同時に、その鮮やかさには感動さえ覚える。
その後には株主資本主義への理論立てに異議を唱え、近年では法や言語への研究にまで及んでいる。対談記事などを読んでいても、「なんと物事を構造的に論理的に明晰に整理しているのだろう」と感嘆してしまうと共に、知を生み出す活動で取り扱う領域の広範さと、とてつもない知識量を以てすれば、確かにこの本の書名が「経済学の宇宙」となっていることに大いに納得。
現在の主流学派である新古典派経済学への反動が起こることがあれば、その時には漸く時代が岩井克人先生の思索に少しは追いつくのではないかと思う。
- 2020年5月10日に日本でレビュー済みAmazonで購入経済学(古典派経済学、新古典派経済学、マルクス経済学にケインズ経済学)から始まって、法学、哲学の話まで、宇宙=Universe=Universityの語源とも言われている=大学を回ってきたような感覚でした。著者にはぜひ東大での講義ノートを出版してほしいです。