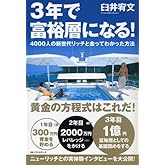・ 本書の出版は2006年でリーマン・ショック以前だが、全体として、着眼点としては今でも参考になる。
・ 2000年頃の例として、大口預金者と小口預金者の対応がほとんど変わらない都市銀行(死語)と、富裕層には駐車場やソファーなど待遇がいい外資系銀行との差異が大きかったことが書かれている。
・ 2000年頃には、ある富豪の夫人が日本に住もうとして、日本には正装のドライバーの24時間サービス、バトラーなどのいるマンションが無く、日本の水準の低さに驚いたとの例を挙げている。
・ また、ハリー・ポッター翻訳者の申告漏れについてもコメントしている。マスコミでは税逃れ目的と報道されていたが、著者は、富裕層向けインフラやサービスが整わない日本よりも、それが整ったスイスをこの翻訳者が選んだ結果ではないかと述べている。個人的には一理ある意見だと思う。とりわけ語学力のある同翻訳者にとってはそうであろう。
・ なお、プライベート・ジェットやクルーズ対応の空港や港湾などの整備が遅れ、サービスも不十分な日本の「観光立国」政策は他国に遅れていると指摘している。もっとも、ドゥバイなどのバブル崩壊を見ると、単に追随すればいいものでもないが。
・ 更に、富裕層にとっての寄付の重要性についてもテッド・ターナー、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、アルフレッド・ノーベル諸氏の行為、キリスト教の「十一献金」などを例に述べており、成金の話だけではなく結構まともである。
・ ところで、著者の臼井氏は自身が経営する企業の未公開株を、必ず値上がりすると偽って売り、2009年に詐欺容疑で逮捕されている。残念ながら、現時点では上記の着眼点も利益が十分上がるビジネスにはつながらないようだ。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

ニュー・リッチの世界 The New Rich World 単行本(ソフトカバー) – 2006/11/21
臼井 宥文
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥1,047","priceAmount":1047.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"1,047","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"0h%2F8egj6uzMQ64p3YBMsjn5HzGU5eB4quWsS47xPe92k00ndmqDFzZiQj4oKeqTegvAPm3SjTJt5OLIsERoBeeqdjr60rMBVkXR4cSBRHuE1nHYrPDNh716p14qFEDZM6%2FSjkld4n3T%2BUQEi5IdRvWCe%2FZSS86k0rN4tPrmAy0J5BI934eOmVg%3D%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}, {"displayPrice":"¥59","priceAmount":59.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"59","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"0h%2F8egj6uzMQ64p3YBMsjn5HzGU5eB4quWsS47xPe92k00ndmqDFzZiQj4oKeqTegvAPm3SjTJuN02EZmlrkUq%2FRat5hYVkQoXIHtSW6kNwln5Lutew5YF5wgOBCc0KliQ9bkFk1pkHDdJe3DcNa8tqVJnpncg%2BZhXpJb17hk5TFasvTV%2FY2gQ%3D%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"USED","aapiBuyingOptionIndex":1}]}
購入オプションとあわせ買い
毎日のように上場企業の社長と食事をする年収3億円の女性ファン
ドマネージャー。ストックオプションで突如、数億単位のおカネを手にした元・
契約社員女性。不況の最中にもかかわらずクルーザーとフェラーリを買うサラ
リーマン。節税対策に1機50億円のプライベートジェットを購入する起業家。暇
つぶしのためにアメリカのスーパーマーケットチェーンを買収した企業オー
ナー。国内には目もくれず、海外の名門校を目指すニューリッチの子どもたち。
いまの日本に誕生したニューリッチたちは、いったいなにを考え、どんなサー
ビスを求めているのか。「富裕層マーケット」という言葉をつくりだした著者
が、国内国外を問わず富裕層たちから見聞きした経験をもとに、彼らの意識に迫
る。
ドマネージャー。ストックオプションで突如、数億単位のおカネを手にした元・
契約社員女性。不況の最中にもかかわらずクルーザーとフェラーリを買うサラ
リーマン。節税対策に1機50億円のプライベートジェットを購入する起業家。暇
つぶしのためにアメリカのスーパーマーケットチェーンを買収した企業オー
ナー。国内には目もくれず、海外の名門校を目指すニューリッチの子どもたち。
いまの日本に誕生したニューリッチたちは、いったいなにを考え、どんなサー
ビスを求めているのか。「富裕層マーケット」という言葉をつくりだした著者
が、国内国外を問わず富裕層たちから見聞きした経験をもとに、彼らの意識に迫
る。
- 本の長さ319ページ
- 言語日本語
- 出版社光文社
- 発売日2006/11/21
- ISBN-104334933955
- ISBN-13978-4334933951
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
登録情報
- 出版社 : 光文社 (2006/11/21)
- 発売日 : 2006/11/21
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 319ページ
- ISBN-10 : 4334933955
- ISBN-13 : 978-4334933951
- Amazon 売れ筋ランキング: - 957,997位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,843位社会と文化
- - 17,868位社会学概論
- - 57,149位投資・金融・会社経営 (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中3.6つ
5つのうち3.6つ
20グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2012年3月10日に日本でレビュー済み
- 2020年6月3日に日本でレビュー済みAmazonで購入出版からしばらく経っていて、どうかなあと読みましたが、高い次元の成功者の実体験(著者含)がとてもわかりやすく書かれていて未来への方向性の参考になりました。今読んでもとても進んだ感覚に没入することが出来るオススメの一冊です。
- 2006年12月28日に日本でレビュー済み富裕層という言葉が使われだして久しい感覚もある。
この書は、実体が分かりにくい富裕層について、国内外の比較とともに将来的展望も投げかけた貴重な一冊です。
しかし、富裕層の実体を紹介する点においては優れているものの、将来に対する提言や見解は、
いささか甘いものがあると言わざるを得ない。
「日本は富裕層への反発心が強い」と述べているが、これは現時点では当然であろう。
貧乏人の僻みと一蹴するのはいかがかと思う。
なぜならば、富裕層以外の国民の多くが最近、将来に対して強い不安感を抱いているからだ。
正社員の減少と派遣社員の増加。雇用システムが変化崩壊していく中で、その日暮らしを
余儀なくさせる人々が増加する一方で、繁栄を謳歌し、一生かかっても使い切れない富を手にする富裕層の増加は、歪んだ社会構造にも思える。
しかも富裕層は、大衆から金銭を稼いで富を得たケースも少なくないので、その富の還元をもっと行うべきだと多くの人も感じていよう。
いみじくも著者自身が、キリスト教などから引用して、富の還元の重要性を指摘している。
この書は、富裕層の実際を紹介する点においては貴重な本であるが、一方的に富裕層だけに焦点を当てて物事を見ている点は、片手落ちであろうと思った。
物事を深く洞察できていない点がある故に、著者の提言するプランも蜃気楼のようにさえ感じられた。
- 2017年7月1日に日本でレビュー済み年収5,000万円以上で金融資産が1億円以上ある人をニュー・リッチと定義付け、その人々に対するビジネスを提唱すると言うのは、ビジネス分野の開拓として良いと思うし、その様な人達の煌びやかな生活を紹介するのは悪くないと思う。
しかし、本書には「日本の新・富裕層」と言う副題がついているにも関わらず、その実態が全く出てこない。ニュー・リッチとなった人々の略歴が全く見えてこないのだ。
極端に言えば、情報商材など得体の知れないビジネスやネットワークビジネスで財を成した人なども、定義で言えばニュー・リッチになるだろう。でも、その様な人達が自身の子供の教育として海外の著名寄宿制学校や著名大学への進学、海外富裕層の集まるパーティーへの参加などへの参加をしているのだろうか?
事実、巻末には著者の会社で発行している雑誌によるアンケートの集計結果が出ているが、そのアンケート結果と本文がほとんどあっていない感じがする。
資産状況に関しては、本文でプライベートバンクを紹介しているが、アンケートの結果ではこれの利用がわずか4.7%。クレジットカードの種類も、プラチナやブラックの保有者は合わせて30%にも満たない。ホームパーティーも51%の人が過去1年間で一度も参加していないと回答。食事の支度は84.2%の人が主に家族が支度。掃除、洗濯もそれぞれ79.2%・87.4%が主に家族がしている。海外経験もほとんど行かないが34.4%、1年に1回が24%と、過半数の人が行ってもせいぜい年1回。子供の留学経験も33.2%の人がさせていなく、させたいとも思わないと回答している。
本書をざっと読むと、日本のニュー・リッチは本国からプライベート・ジェットで来るような子供達ばかりの様なイギリスやアメリカ、スイスの寄宿制学校に進学させ、早稲田・慶応・東大などでは無く海外のランキング上位校に進学させる。自身もプライベート・ジェットやクルーザーを所有し、超高級車をキャッシュでポンと買い、本宅以外に海外に別荘や別宅を持ち、季節や行事にあわせてプライベート・ジェットで移動している様なイメージになる。しかし、実態は著者の発行している雑誌の読者(当然、読者で回答者の中には年収1,000万未満の人も居るが、総資産が7,000万円未満の人はわずか1.6%)の回答の様に、別にホームパーティーに参加する訳でも無く、家政婦を雇って家事を任せる訳でも無く、ハイライフ・カレンダーの予定通りプライベート・ジェットで海外を飛び回り、F1観戦やその後のパーティーに興じている訳でもないと言う事だ。
ニュー・リッチと言う定義は面白いが、紹介事例はスーパー・リッチの事例や恐らくは王侯貴族や資産家令嬢などオールド・リッチに属する人々の華やかな生活で、ニュー・リッチの世界は全く見えてこなかった。
- 2007年1月8日に日本でレビュー済み金融資産1億以上5億以下をニュー・リッチと定義し、それについて分析を進めるのかと思いきや、エンエンと桁外れの金持ちの話ばかり。(例;金融資産5億円以下の人に50億円のプライベートジェットは手が出ないはず)ソウと割り切って読めばそれなりに勉強になるでしょうが。。。副題は「金融資産10億以上の人々」とするべきでした。1−5億のクラスでは、筆者がここで触れるような派手な生活を好む人ばかりではないと思います。私も含めもっと普通の質素な生活の人も多いはず。
また教育の話をするなら欧米の(高校や大学だけではなく)ビジネススクールについても触れて欲しかった。
- 2009年1月15日に日本でレビュー済み日本の富裕層を紹介する本としては良いのだろう
富裕層の求めるもの、富裕層の生活、日本と米国の富裕層の生活の違いなどを解説してくれる。
様々な切り口から富裕層を見ている点は高評価。
しかし、客観的な情報しかこの本には書いてない印象がある
作者の意見をもう少し混ぜながら本を執筆していけばもう少し優良な本が書けたと感じる。
加えて、日本語と英単語を混ぜながら文章を書いている意味が解からない。
作者が英語を出来るのを自慢してるように感じた。
英単語が混ざっているので慣れるまで、読みにくい印象を受けた。
- 2007年8月31日に日本でレビュー済み「年収5000万円以上、金融資産1億円以上」の人々は、どんなものを求めているのか?
統計上は世界有数の「富裕層大国」であるはずの日本。それなのに、富裕層(特に、上昇志向が強い新興の「ニューリッチ」)が求めるものを提供できていない現実が良く分かる。
ニューリッチの生活は、庶民からすると驚きの連続。プライベートジェットなど、どうやったら買えるのだろう。圧倒されながらも「いつか自分も」という夢に浸ることができる(実現は難しそうですが)。特に、富裕層子女の教育にかかる部分は、非常に考えさせられる。低レベルの教育からは低レベルの人材しか生まれてこないとしたら、将来の日本にとって大問題だ。
最近盛り上がっている「格差論議」では、貧困の拡大ばかりが問題とされ、本来、豊かな文化の担い手であり、雇用の創出、高額な税負担、旺盛な消費などを通じて、日本の経済・文化に多いに貢献している富裕層のあり方については問題とされることが極端に少ない。妬みから富裕層の足を引っ張り、経済発展のチャンスを逃し、文化を衰退させ、彼らを国外脱出させることが本当に正しいことなのか。一億総中流の社会が現実的に終焉した今、真剣に考えてみるべきだろう。
ニューリッチの世界を垣間見る楽しさと、富裕層のニーズに応えられていない日本の寂しい現状。そして、そんな状況だからこそ、無限に広がる富裕層ビジネスの可能性について考えさせられる本。下流本も自虐的で楽しいですが、こちらの方は夢があり、面白いですよ。
- 2007年2月14日に日本でレビュー済み超富裕層の生活、世界。
知りませんでした。知らないで、家庭や学校で教えられた
ような経済法則や生活倫理を信じて生きているのが幸福
なのか。はたまた、そういう刷り込みとは別の世界、生き方、
交流があることに気がつき、それを手に入れて生きるのが
幸福なのか。
本書は、平均的な庶民に、世界レベルでの格差、搾取、
また教育による格差を、これでもか、というほど具体的に
描いていて、目からうろこが落ちる思いです。
庶民はやはり小金持ちとか、プチ富豪レベルの価値観、生活
が身の丈にあっているような気もする一方、超リッチな世界で
生きていくのも、たぶん、それなりの気苦労があるのかもしれませんね。
本書は、そういった超リッチ階層の心の世界を垣間見ることはして
いませんで、生活、趣味、価値観、経済法則からの自由など
どっちかというと物理的な面を詳しく描き出しています。
中盤に懇切丁寧に解説している富豪子息教育のすごさ、と
富裕層マーケティングは読んでいてとっても面白いです。
自らが超リッチになれなくても、富裕層向け事業を仕掛けると
いうことは庶民にも可能なのでしょうか。でも、リッチな視点を
もっていないと、なかなか満足させられないかもしれませんね。