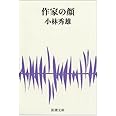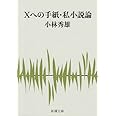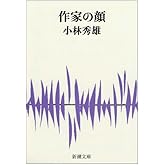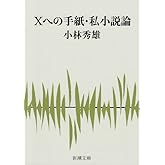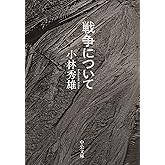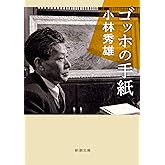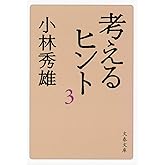初期の小林秀雄と言えばマルクス主義文学を横目ににらみながら自分の文学理論を確立しようとしていた頃。私の一番好きな時期でもある。
小林はよく「生き生き」とか「血」「肉」という言葉を使う。小林が尊敬する文学が生き生きした存在を活写した作品であり、その文体自体が生きている、そういうものだ。
小林自身の文章も当然、生き生きとした知性が息づいている。仮に小林が間違っていようと、勘違いしていようと、この人間は自分の知性で自分の道を進んでいく人間だと、読んでいる人間には気づくだろう。それに気づかない人はイデオロギーに頭をやられているからだ、と、こういう言い方は初期小林秀雄的である。マルクス主義を現代の様々な通俗主義だと読み変えてしまえば、小林秀雄の理論が今も生きている事に気づく。(それが古典というものだろうが)
小林秀雄は初期の文芸時評には途中で見切りをつけた。わかりやすく言えば、雑魚を相手にするのに飽きたという事だろうか。もちろん同時代の尊敬を払うべき作家には丁重だが、彼は、いわば釣り師としてもっと大きな獲物に飛びかかりたくなったに違いない。それがドストエフスキーであり、後のゴッホだったりした。そういう変転がある。
ただ、初期の小林は闘争的であり、同時代的であり、一番生き生きとした活力を感じさせる。今もいろいろな事を考えさせる好論文ばかりだ。私は読み返して葛西善蔵・嘉村磯多への評論に改めて教えられる思いがした。
文学志望の人間は必読、と言いたいところだが、彼らはこういう論文は決して読みはしまい。彼らは、新人賞を取る為に現代の三流作家を尊敬するところから始める。その為に「どいつもこいつも通俗小説しか書いてねえじゃねえか」と、小林秀雄の啖呵が今でも通用する事になる。愚かさが変わらない以上、愚かさを切り捨てる賢さの味わいも変わらない。今も小林秀雄を読み返す価値はきっと、あるだろう。
この注文でお急ぎ便、お届け日時指定便を無料体験
Amazonプライム無料体験について
Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
新品:
¥935¥935 税込
発送元: Amazon.co.jp 販売者: Amazon.co.jp
新品:
¥935¥935 税込
発送元: Amazon.co.jp
販売者: Amazon.co.jp
中古品 - 良い
¥508¥508 税込
無料配送 5月26日-28日にお届け
発送元: 買取王子 本店 販売者: 買取王子 本店
中古品 - 良い
¥508¥508 税込
無料配送 5月26日-28日にお届け
発送元: 買取王子 本店
販売者: 買取王子 本店

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

批評家失格―新編初期論考集― (新潮文庫) 文庫 – 2020/7/29
小林 秀雄
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥935","priceAmount":935.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"935","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"%2F8tXXMyC0X8cJrDwL24RWjwoJcoL%2Fj2ny7ZteF79L3aW1PZLd292lDt2OWIaK5XLTPsc1UnI6Ym9bDsTEcMiDADo2Nh6Eas3IZM8iBuhtdn%2B%2BXGkutuaST6sPp2Kbvo%2FdU4daY9s0Q4%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}, {"displayPrice":"¥508","priceAmount":508.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"508","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"%2F8tXXMyC0X8cJrDwL24RWjwoJcoL%2Fj2nl%2BZu7AR3LIvuKdUpVrmfjdRAu4x%2FgidMioRDbbBEgIS2mMbB%2FqwBDfeg%2BwmLhJuyQ4sHedyYVqg0kmHbR%2BoSTstzjcS%2BrzG6Ca36LOCSLRf%2BdUczS51grdbh5Pt1bm%2BzOELGsr3LB9AcCoDLH5n7KA%3D%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"USED","aapiBuyingOptionIndex":1}]}
購入オプションとあわせ買い
小林秀雄の慧眼は批評を、分析でも悪口でもなく、愛情と感動だと喝破した。芸術に対峙し、心打たれることに意義を見出す。この近代批評の確立者も当初、生計を支える稼ぎ手として書く。東大新聞の下品な問いにも不機嫌さを隠さず応じた。一方で美に昏い世を警醒し続ける。人間的な素顔の窺える文庫初収録随想と入手困難だった批評を併せて収録。22歳から30歳まで、瑞々しい52編の文芸論集。
- 本の長さ576ページ
- 言語日本語
- 出版社新潮社
- 発売日2020/7/29
- 寸法10.6 x 1.7 x 15.1 cm
- ISBN-104101007128
- ISBN-13978-4101007120
よく一緒に購入されている商品
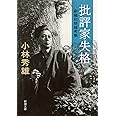
対象商品: 批評家失格―新編初期論考集― (新潮文庫)
¥935¥935
最短で5月24日 土曜日のお届け予定です
残り3点(入荷予定あり)
総額: $00$00
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
一緒に購入する商品を選択してください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
出版社より

作家の顔
|

ドストエフスキーの生活
|

モオツァルト・無常という事
|

Xへの手紙・私小説論
|

本居宣長〔上〕
|

本居宣長〔下〕
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.5 16
|
5つ星のうち4.3 41
|
5つ星のうち4.1 179
|
5つ星のうち4.4 30
|
5つ星のうち4.2 123
|
5つ星のうち4.2 90
|
| 価格 | ¥781¥781 | ¥1,100¥1,100 | ¥693¥693 | ¥737¥737 | ¥1,045¥1,045 | ¥990¥990 |
| 【新潮文庫】小林秀雄 作品 | 書かれたものの内側に必ず作者の人間があるという信念のもとに、鋭い直感を働かせて到達した作家の秘密、文学者の相貌を伝える。 | ペトラシェフスキイ事件連座、シベリヤ流謫、恋愛、結婚、賭博──不世出の文豪の魂に迫り、漂泊の人生を的確に捉えた不滅の労作。〈文学界賞受賞〉 | 批評という形式に潜むあらゆる可能性を提示する「モオツァルト」、自らの宿命のかなしい主調音を奏でる連作「無常という事」等14編。 | 批評家としての最初の揺るぎない立場を確立した「様々なる意匠」、人生観、現代芸術論などを鋭く捉えた「Xへの手紙」など多彩な一巻。 | 古典作者との対話を通して宣長が究めた人生の意味、人間の道。「本居宣長補記」を併録する著者畢生の大業、待望の文庫版! | no data |

近代絵画
|

批評家失格─新編初期論考集─
|

ゴッホの手紙
|

人間の建設
|

直観を磨くもの―小林秀雄対話集―
|

学生との対話
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1 51
|
5つ星のうち4.2 31
|
5つ星のうち4.0 33
|
5つ星のうち4.4 747
|
5つ星のうち4.0 115
|
5つ星のうち4.5 101
|
| 価格 | ¥1,045¥1,045 | ¥935¥935 | ¥990¥990 | ¥572¥572 | ¥770¥770 | ¥605¥605 |
| モネ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーガン、ルノアール、ドガ、ピカソ等、絵画に新時代をもたらした天才達の魂の軌跡を描く歴史的大著。〈野間文芸賞受賞〉 | 近代批評の確立者、批評を芸術にまで高めた小林秀雄22歳から30歳までの鋭くも瑞々しい論考。今文庫で読めない貴重な52編を収録。 | ゴッホの絵の前で、「巨(おお)きな眼」に射い竦すくめられて立てなくなった小林。作品と手紙から生涯をたどり、ゴッホの精神の至純に迫る名著。〈読売文学賞受賞〉 | 酒の味から、本居宣長、アインシュタイン、ドストエフスキーまで。文系・理系を代表する天才二人が縦横無尽に語った奇跡の対話。 | 湯川秀樹、三木清、三好達治、梅原龍三郎……。各界の第一人者十二名と慧眼の士、小林秀雄が熱く火花を散らす比類のない対論。 | 小林秀雄が学生相手に行った伝説の講義の一部と質疑応答のすべてを収録。血気盛んな学生たちとの真摯なやりとりが胸を打つ一巻。 |
商品の説明
出版社からのコメント
「様々なる意匠」で彗星のごとく文壇に登場したのは、昭和4(1929)年、小林27歳の時。以降、「文藝春秋」で大抜擢を受け文芸時評欄を担当する。同時代文学を俎上に鋭い論考を発表し始めた。とはいえ、月々の文芸雑誌を読み、批評する時評稼業が小林の目指すところであるわけもなく、やがて彼は自らの、オリジナルの仕事に目を向けて歩き出す。文芸時評をケージの中で生産し続ける批評家(=時評家)稼業に見切りを付けるのが、昭和7(1932)年の暮れで、翌8年からは、ドストエフスキーに関して論考を重ね始める……。 本書は大正13(1924)年から昭和7年まで、小林秀雄22歳から30歳までの8年間に発表された作品のうち、これまでに一度も文庫に収録されなかった貴重なエッセイと、かつて文庫に収録されたことはあるものの現在入手困難となった重要な論考を併せて一巻の論考集とした。後の小林秀雄の思考の基礎をなす原初的感覚が30歳までの初々しい論考の中にすべて埋まっていることに改めて驚かされる。
登録情報
- 出版社 : 新潮社; 文庫版 (2020/7/29)
- 発売日 : 2020/7/29
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 576ページ
- ISBN-10 : 4101007128
- ISBN-13 : 978-4101007120
- 寸法 : 10.6 x 1.7 x 15.1 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 123,937位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 154位論文集・講演集・対談集
- - 2,321位新潮文庫
- - 33,215位ノンフィクション (本)
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

1902‐1983。東京生れ。東京帝大仏文科卒。1929(昭和4)年、「様々なる意匠」が「改造」誌の懸賞評論二席入選。戦中は「無常という事」以 下、古典に関する随想を手がけ、終戦の翌年「モオツァルト」を発表。’67年、文化勲章受章。連載11年に及ぶ晩年の大作『本居宣長』(’77年刊)で日 本文学大賞受賞(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『 人間の建設 (ISBN-13: 978-4101007083)』が刊行された当時に掲載されていたものです)
カスタマーレビュー
星5つ中4.2つ
5つのうち4.2つ
31グローバルレーティング
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2022年4月4日に日本でレビュー済み20代のころのエッセー集。
40年前、学生の頃に小林秀雄を初めて読んで文章が難しいなあという感想を持った。
それ以降も何冊か読んだが感想は同じ。
今回も同じで、正直文章硬いし面白くない。
余り中身がないように思うのだが・・・
- 2023年12月6日に日本でレビュー済み彼の「批評家失格」は深い苦悩を裡に秘めつつ孤軍奮闘している時期に書いたものだ。
――「今や私は自分の性格を空の四方にばら撒いた、これから取り集めるのに骨が折れる事だろう。」このボードレールの言葉を小林秀雄は「✕への手紙」に引用し、さらに自らを「――俺は今この骨の折れる仕事に取りかかっている。もう十分に自分は壊れてしまっているからだ」と告白する。骨の折れる仕事とは何か、それは単に「いかにかすべきわが心」という思いで佇み、身動きしないというわけにはいかぬ。言わばいかにこの世が「地獄絵」で、それを全身で感じ、観た者はただ「虚空遍歴」などするわけにはいかぬ。
百年前だったらランボーのように砂漠へと、人々に別れを告げ、ざらざらとした現実の中でのたうち、自減出来たかもしれぬが、時すでに遅く「前例」がいる。――断じて架空のオペラを演じない事。それにしても、自己のバラバラになった意識をいかに生々しい現実の中に復活させるか?変容せしめるか?果してその受け継いだ「事業」をどこまで成し得るか?ここで小林秀雄の自己自身の内的戦いの末の表明が、覚悟があの「批評家失格」という文章を書かせた。
「――地獄絵の前に佇み身動きも出来なくなった西行の心の苦痛を、努めて想像してみるのはよいことだ」と。
これはそのまま小林秀雄自身の姿にも当てはめることが出来る。彼は相手の眉間を割る覚悟はいつも失うまい、と言った。だが彼は一度たりとて相手の眉間を割ったことはない。彼に対する攻撃の急所、隙はまさにここにある。情の脆さである。その脆さが、その情が深く緻密でなければ人生を達観する「仙人」と化す。仙人面した物分かりの良い浅はかな人種、それを彼はインテリと呼んだ。それにしても、それにしてもである、彼は相手の眉間を割ることは無く、常に「寸止め」をする、――
他人を切り刻む前に自分を徹底的に切り刻んでいるからだ。彼が論じたランボオ然り、ニーチェ、西行、その他然り――。彼の取りあげた人物達には自己の宿命と似た所謂「愛と認識の殉教者」が多かった。同じ心、つまり「いかにかすべきわが心」の思いをもって人生を「のたうちまわった」人物達の魂が、その思いが小林秀雄の表現の原動力であった。だから「探る眼はちっとも恐かない、私が探り当ててしまった残骸をあさるだけだ。」とか、「私は、理智を働かせねば理解出来ぬような評論を絶えて読んだ事がない(私の評論などは言わずと知れたこの部類だ)」(拙著小林秀雄論より抜粋)
彼の評論は難解とか断定する等の種々、賛否が多い。或いは、歴史上の天才的な人物しか扱っていない、と。
しかし、下記のランボオについて書いたものは紛れもなく彼自身の本音であり、己の宿命と刺し違えた、言語表現の原動力である。
「ランボーⅢ」の中で小林秀雄ははっきり明言する「――彼は河原に身を横たえ、飲もうとしたが飲む術がなかった。彼はランボオであるか。どうして、そんな妙な男ではない。それは僕等だ、僕等皆んなのぎりぎりの姿だ。」と。
- 2020年10月3日に日本でレビュー済み1983年に小林秀雄が亡くなってから10年ぐらいは、死せる孔明生ける仲達を走らす感があったほど、人気が沸騰していた。とくに初期の文芸批評が注目されたし、僕も好んで読んだ。何と言っても現実世界でいけなくなった社会主義国の時代から、所謂ソビエトマルクス主義の批判が共有され、やや保守系の論客はもちろん、新左翼的な論客も、過去の共産主義者には批判的だったのだが、過去の内ゲバ的な批判の応酬より、小林秀雄のような門外漢の言説が、風通しがよく、面だの小手だのに、ビシビシ決まっている批判が現代になっても読むに堪え得た。当時まだ存命で人気絶頂だった吉本隆明や柄谷行人も、小林秀雄の影響下に批評家になっているだけあって、彼らの小林評価も、その初期に対して高かったこともオピニオンリーダーとして効いていたと思う。
時を経て、手に取りやすい文庫で、その時代の批評が出てきたので、30年ぶりに読んでみると、もはや、興味はそういう、内容的な筋のはなしではなくて、当時の言説の場みたいなものが、浮かび上がってきて興味深かった。昭和前期の、或る種の文化史だと思う。
若い小林さんは、すごい早熟・成熟振りで、とても若年には思えな風格、言論界の飛び交う言葉から距離を取りつつ理解を外さない、大物ぶりにはびっくり。自身に対する批判や皮肉や中傷にたいしても動じない風格がある。が、注意して読んでいると、大宅壮一みたいな、所謂専門の無い批評家みたいなのには、やや苦手なのか、イライラ感が透けて見えて、やっぱり人の子だ、と思ったものだ。
小林秀雄の軍門?に下らなかった売れっ子の批評家が二人いる。清水幾太郎と伊藤整だ。清水については、分野も違うことがあって、一回ぐらい肯定的な言及があったと思うが他は無いと思う。一方、伊藤整については、本書にも、嫌みで意地悪な言説が載っているが、こういうのを読むと、なんというか、これまた小林秀雄も人の子だ、と思う。なんとなく僻みっぽい感じのする批評で言わずもがなの感じだ。ジョイスの意識の流れなんてのに苦労して翻訳なんかする新しもの好きなんかより、今までの文学の理解で、それぐらいのことはわかるだろう、ぐらいの感じである。小林も別所で書いているように、人は意地が悪くなる時は気が緩んでいるので、この批評も珍しくだれていた。
新潮文庫の小林秀雄は30年1日のごとき、お決まりの数冊ばかりで、荒稼ぎしていたが、本書を出したので、少しは、やる気が出てきたのかな、と思った。
- 2020年8月1日に日本でレビュー済み小林秀雄に限らず、司馬遼太郎、松本清張など、人気だけでなく尊敬を集めた作家はもう日本にはいない。以前、小林秀雄の大作『本居宣長』を読み始めたのだが、数ページでダウンしたことがある。そこで今回は、短編集ならば読めるだろうと再チャレンジした。
1.批評と評論
どれを読むべきか見当もつかないので、タイトルになった「批評家失格」を読み始めた。この論考には、新潮社で小林秀雄担当であった池田雅延氏の「解説」の中で、次のように説明が加えられている。
小林は‘批評家’という言葉を使っているが、これは‘評論家’のことである。評論家は時評家と同じで、他人を論う(あげつらう)ことをもっぱらとする。だから自分は評論家になれないという意味で「批評家失格」としているのである。
評論家は「けなす」が、批評家は「ほめる」るのだ。「けなす」ことは「昨日までと変わらぬ自分が力むだけである(p.558)」が、「ほめる」ことは「自分を知るため、生き方を模索するため(p.557)」なのである。
そういえば、私がカスタマーレビューを書くのも、その本を読んでもらいたいためである。「ほめる」ためで、「けなす」ためではない。だからほとんどが5つ星となる。
2.自然主義小説は可能か
解説は池田氏の「解説」ばかりでなく、註解がp.439からp.551にかけて詳しく施されている。難解な論考を読みこなす助けになっている。それをペラペラとめくっていると、‘自然主義’の註解を見つけた。自然主義は理系のはずであり、文系の小説とは相容れないはずだ。小林がこの点をどう考えているか、自然主義の文字を探してみた。
「芥川龍之介の美神と宿命」の註解に、「自然主義 19世紀後半、フランスを中心として興った文芸思潮・運動。自然科学の成果と実証主義に則り、自然的・社会的環境下にある人間の現実を客観的に描こうとした」とある(p.453)。
小林の見解は「谷崎潤一郎」の論考の中にある(p.299-301)。もちろん谷崎をほめるためである。「本国(フランスなど)では、....底にまさしく野心的な社会的イデオロギイを蔵していた。作家は例外なく野心的な社会小説を書いた。....わが国に輸入された自然主義文学なるものは、....技巧上の一形式に過ぎなかった....多くの作家は最初から自我に固執した。....実証精神は社会の構造に向けられず、意識の検討に向けられた、....自然文学に関して、心境小説、身辺雑事小説の日本独特の専門語が発明された所以である。」と述べている。
小林は自然主義文学を評価していないようだ。海外では自然的・社会的環境下にある人間の現実を客観的に描こうとしたが、わが国では描く対象を自我や意識に向けた。
思うに、自我や意識という文系の対象を、自然主義の方法で捉えたものに精神分析があったが、フロイトの『精神分析』は1917年の出版であり、日本語への翻訳は1928年になる。自然主義文学の代表作、島崎藤村『破戒』は1906年、田山花袋『蒲団』は1907年で、精神分析が彼らに影響を与えることはできなかった。もし精神分析が背景にあれば、自然主義文学は短命で終わることはなかったかもしれない。
ここで小林は文系・理系の区別を持ち込まないが、文系内での社会系・心理系の区別をしている。19世紀末の本国フランスなどの自然主義文学は、ダーウィンの『種の起源』1859年、ベルナールの『実験医学序説』1865年などの影響の下に、自然科学の方法論・実証精神を持ち込もうとした。日本の失敗の理由は、方法論と対象のミスマッチにあるのではないか。
小林秀雄の作品は、8月末に『ゴッホの手紙』が、9月末に『近代絵画』が刊行予定だそうだ。こちらも楽しみである。