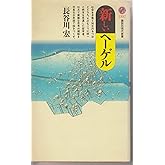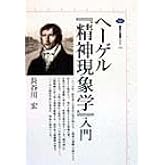ヘーゲルの翻訳を中心に活動している「在野の哲学者」である著者が、岩波市民セミナーにおいて4回に渡って行った講義を大幅に改稿したものである。セミナーの雰囲気が十分伝わってくる。参加者との質疑応答が、各章に「対話」として付されているが、参加者の関心の深さとレベルの高さはなかなかのものである。全体として、著者の専門であるヘーゲルの視点に立ち、当時のドイツの支配的思想であるヘーゲルの観念論的弁証法から、初期マルクスが脱却するための思想的営為を追っている。
著者は、ヘーゲル哲学の4つの特徴として、人間主義、合理主義(ないし理性主義)、現実主義、および進歩主義をあげる。このような前向きの思想としてのヘーゲルを引き継ぎつつも、歴史を大きく包み込む近代を肯定的に捉えるヘーゲルに対して、マルクスは強い違和感を持つ。この違和感を具体的に理論化する過程が、初期マルクス(およそ20歳代)の思想的営為である。本書で著者は、マルクスのヘーゲル批判・近代批判を、マルクスの人間観・自然観とのつながりで考える、という立場をとる。つまり、本書では、マルクスが資本主義批判に至る前段階を考察していく。
第2章では、『経済学・哲学草稿』に沿って、「疎外された労働」について考察を進める。この草稿はマルクスの死後に出版されたものであるが、著者は、この本の中に、マルクスが哲学的視点から、19世紀の社会や経済に対して根本的な批判を加えた貴重な内容が含まれていることを強調している。「疎外された労働」が最も非人間的な疎外であることを考え抜いたマルクスは、人間的な労働を回復するには、社会の根本的な改革以外ににはないことに思い至り、こうして『共産党宣言』や『資本論』への道が拓かれていく。
第3章では、『経済学・哲学草稿』の中に現れたマルクスの人間像について紹介する。若きマルクスが、私有財産の支配する資本主義社会を乗り越えて、その先にどのような人間社会を目指すべきかを、様々な視点から考察している。その中には、男女の関係のあり方や死への見方など、あまり後には論じられない視点も含まれる。また、人間の感覚も社会的な関係に組み込まれたものとして捉えている点などは興味深い。
本書を読み、マルクスの思想は、歴史上の社会主義国が失敗したかどうかには関わりなく、現代社会までに射程距離を有する稀有な思想であることをあらためて痛感した。
この注文でお急ぎ便、お届け日時指定便を無料体験
Amazonプライム無料体験について
Amazonプライム無料体験について
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥460 - ¥500* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

初期マルクスを読む 単行本 – 2011/2/25
長谷川 宏
(著)
このページの読み込み中に問題が発生しました。もう一度試してください。
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥2,530","priceAmount":2530.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"2,530","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"QLpcp%2FblFO5%2BQy3dZrRZz3vZ%2BaREPVRKiXfvU02r024u5UBbfOPzAZVbIWXdm1H0V5rzZ66XQcX1ead39ZfqnfHBVo%2BNMeRcHoGu2ltg2i8bt7hG7RQYyEXlEyHO941xE3S7v2D0Qbc%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}, {"displayPrice":"¥315","priceAmount":315.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"315","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"QLpcp%2FblFO5%2BQy3dZrRZz3vZ%2BaREPVRKN8tJda8LG0fTszCOPV2YJvNMTkEcvQNnjQK3PzxP3g%2BLyHqQE%2FeTAVXeNlKuWTM62%2ByzLso0WcnsTawGVVyeyQrXhPBY00QY7wnMrMwC0CIYtT%2BUbTqqyC%2BDrsDH%2FrvwFOR87csQzPEiBYP6BvkXg0yQLOmzqsxm","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"USED","aapiBuyingOptionIndex":1}]}
購入オプションとあわせ買い
今日に生きる、人間性の回復と再生の思想
- 本の長さ216ページ
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2011/2/25
- 寸法13.5 x 2.2 x 19.5 cm
- ISBN-104000234862
- ISBN-13978-4000234863
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1 / 1 最初に戻るページ: 1 / 1
商品の説明
著者について
長谷川 宏(はせがわ ひろし)
1940年生まれ.専攻は哲学.東京大学大学院博士課程単位取得退学後,大学アカデミズムを離れ,在野の哲学者として,多くの読書会・研究会を主宰する.また,41年間続く私塾・赤門塾は,ユニークな活動をもって知られる.
主著,『ヘーゲルの歴史意識』(紀伊國屋書店,のち講談社学術文庫),『黒田喜夫――村と革命のゆくえ』(未來社),『同時代人サルトル』(河出書房新社,のち講談社学術文庫),『ヘーゲルを読む』(河出書房新社),『丸山眞男をどう読むか』(講談社現代新書),『日常の地平から』(作品社),『高校生のための哲学入門』(ちくま新書),『生活を哲学する』(岩波書店),『ちいさな哲学』(春風社)ほか.
訳書,フッサール『経験と判断』(河出書房新社),ヘーゲル『精神現象学』(作品社),『哲学史講義』全3巻(河出書房新社),『美学講義』全3巻(作品社),『歴史哲学講義』全2巻(岩波文庫),マルクス『経済学・哲学草稿』(光文社古典新訳文庫)など.
1940年生まれ.専攻は哲学.東京大学大学院博士課程単位取得退学後,大学アカデミズムを離れ,在野の哲学者として,多くの読書会・研究会を主宰する.また,41年間続く私塾・赤門塾は,ユニークな活動をもって知られる.
主著,『ヘーゲルの歴史意識』(紀伊國屋書店,のち講談社学術文庫),『黒田喜夫――村と革命のゆくえ』(未來社),『同時代人サルトル』(河出書房新社,のち講談社学術文庫),『ヘーゲルを読む』(河出書房新社),『丸山眞男をどう読むか』(講談社現代新書),『日常の地平から』(作品社),『高校生のための哲学入門』(ちくま新書),『生活を哲学する』(岩波書店),『ちいさな哲学』(春風社)ほか.
訳書,フッサール『経験と判断』(河出書房新社),ヘーゲル『精神現象学』(作品社),『哲学史講義』全3巻(河出書房新社),『美学講義』全3巻(作品社),『歴史哲学講義』全2巻(岩波文庫),マルクス『経済学・哲学草稿』(光文社古典新訳文庫)など.
登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2011/2/25)
- 発売日 : 2011/2/25
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 216ページ
- ISBN-10 : 4000234862
- ISBN-13 : 978-4000234863
- 寸法 : 13.5 x 2.2 x 19.5 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 255,601位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 2,881位哲学 (本)
- - 5,077位その他の思想・社会の本
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

著者の本をもっと見つけたり、似たような著者を調べたり、おすすめの本を読んだりできます。
カスタマーレビュー
星5つ中4.5つ
5つのうち4.5つ
6グローバルレーティング
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星5つ84%0%0%16%0%84%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星4つ84%0%0%16%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星3つ84%0%0%16%0%0%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星2つ84%0%0%16%0%16%
- 星5つ星4つ星3つ星2つ星1つ星1つ84%0%0%16%0%0%
評価はどのように計算されますか?
全体的な星の評価と星ごとの割合の内訳を計算するために、単純な平均は使用されません。その代わり、レビューの日時がどれだけ新しいかや、レビューアーがAmazonで商品を購入したかどうかなどが考慮されます。また、レビューを分析して信頼性が検証されます。
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中にエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
- 2014年6月12日に日本でレビュー済み
- 2011年5月10日に日本でレビュー済みドイツ観念論は考える時の構図の設定の仕方に特徴があり、それは単独の個人を考える主体として設定することであり、こうした構図が成り立つのは、近代的な個人が人々の中で十分、理解されていたから、というあたりの整理はなるほどな、と(p.10)。ヘーゲルには《歴史を大きく包みこむ近代》という壮大なイメージがあるのですが(p.19)、マルクスは近代を強く肯定できない。そこがマルクスのヘーゲルに対する違和感になっていく、と(p.20)。ヘーゲルの『法哲学要綱』では、家族や市民社会というのは矛盾に満ちたものだが、最後に国家が大きく覆いをかけて全ての矛盾を解決する、という展開になっているのですが、そうしたところにもマルクスは強い違和感を覚えて、批判します(p.28-)。そして民衆が最も地に足がついた存在してある、というのが『ヘーゲルの法哲学批判序説』だというのが長谷川さんの解説。
また、『ユダヤ人問題について』では、強烈な金銭的価値観をアイデンティティとして持っていることを認めつつ、それをどう乗り越えていくを考えるというのが主題である、というのもわかりやすかったでが(p.38)、やはり、ご自身でも翻訳されている『経・哲草稿』に一番、熱が入っていましたね。
マルクスは《多くの人がいて、互いに言葉を交わし、共同作業する。そんな人間というものの総体はいったいどうやって登場したのか》(p.94)というあたりから、《労働そのものが、歴史を貫いて人間世界に大きな広がりをもたらし、人間のあいだをつなぎ、人間と自然とのあいだをつないでいく、本質的な活動だ》と考えたのですが、それが《これほどにも豊かなものであるはずの労働が、近代社会のなかではこれほどにもゆがめられ、つぶされていく》(p.97)ことに怒りを覚えたというあたりの書きっぷりは好きです。
- 2011年4月3日に日本でレビュー済み在野でありながら、わかりやすいヘーゲルの訳で高名な長谷川宏氏が、初期マルクスを論じた本ということで並々ならぬ期待を持って読んだ。しかし、マルクスが人間疎外を分析する道具として用いた「人間」、「自然」、「労働」などの概念が、日常語のように解説されているところが多く違和感を感じた。「五感の形成はいままでの全世界史の労作である」という言葉について、私は、人は労働を通じ自然と関わることで人間を作ったと理解していた。この理解では、自然は主体としての人が関わる対象全体を意味し、労働は対象に関わることそのものを、五感は動物と区別される人間の本質を意味する。しかし、長谷川氏は、自然を、「自然に恵まれ、……自然との交流のなかで生きる」というように、狭義の自然ととらえているようだ。同様に、労働も、「現代を生きているわれわれとしては、労働が生活の全体を覆うという社会的なイメージをもつことは少し難しい。遊びやレジャー、あるいは趣味というものが、マルクスの時代と比較すれば大きな位置を占めている」と、余暇と対比される意味での労働ととらえている。「五感の形成」も、「感覚を論じようとするとき、おいしいけれど、……前にどこで食べたときに味わったのだろうかと思いめぐらしている場合には、まさにいま感覚しているこの楽しさやこのおいしさが問題なのです。その場合には、歴史的な視点が常に有効だとは限らない」と、狭義の意味での感覚の問題とされてしまう。「人間の本質とは現実には社会的関係の総体である」という言葉についても、「(日本のように)個人と自由と自立が確立していない社会風土で、人間の本質が『社会的関係の総体だ』という文言に接すると、個人を社会に埋没させるような全体主義的な理解に道を開くおそれがないとはいえない」という危惧を抱いている。しかし、マルクスは、キリスト教の本質は人間の本質であるとしたフォイエルバッハを批判して人間の本質は社会的関係の総体であると述べており、「社会的関係」は、個人を取り巻く社会的関係よりも、個人に内在化された社会的関係に重点があると理解すべきではないだろうか? 分析の道具としての概念を、日常語のように理解した場合には、マルクスが分析を試みた人間疎外も表面的な理解に終わってしまうのではないだろうか。
- 2011年3月21日に日本でレビュー済み「経済学哲学手稿」と、その前の「国法論批判」「法哲学批判序説」「ユダヤ人問題」そして、「ドイツ・イデオロギー」を参考に論じられる。「資本論」や「経済学批判」も終盤少しだが取り上げられる。引用の原典についての著者の翻訳も、地の文章も、ちゃんとした日本語で、読めばイメージを伴うことができるので読みやすい。論じられている「初期マルク」は雲霞のごとく著書もあり、翻訳も数種類あるし、優れた論文もあるので、本書で新奇の知識というのは得ることはないと思う。本書の面白さは、若いマルクスの目線を大事にしながら、その感性が思想になって行く様を描いているところだと思う。だいぶ前に著者は「ヘーゲルの歴史意識」を言う名著を書いているが、その時も無名のヘーゲルの感性と思想の生成を書いてくれていてやはり面白かった思い出がある。で、本書だが、そんなわけで、言葉をとても大事にしている。たとえば、ヘーゲルのSittlichkeitとマルクスのGesellschaftlichkeitの対比で説明するところは面白かった。また、個人の社会化や、その裏面をなす社会の主体化についてへーゲルは詳しく論じているが、「そのことを人間の感性にまで踏み込んで考えるのがマルクスの新しさではないか」として、「人間の対自然の関係のなかに、人間と人間の関係を組みこむ」ところにマルクスの独自性を指摘して、マルクスの感覚論に話を運ぶくだりは、本書のなかで最も印象深いところだった。40年ほど前には、同じようなマルクスの感性論を論じた論文もあったし、或る意味吉本隆明の「マルクス論」もそういうところはあるのだが、本書の魅力は、マルクスの感覚に対する視点が、人間の生活の営みに目が向けられており、それを思想へと織りなす過程を描いている点にあると思った。読後の問題意識を言うと、1)ヘーゲルが大変「近代」というものを信頼し、理性というものを信じているが、マルクスはそうではなかった、という点に対比を示すところは、穏健な普通の見方だが、ヘーゲルの「法の哲学」の<欲求の体系>で論じられる「市民社会」の問題点はマルクスとあまり変わらない深刻さを認識していると思う。2)同じく「法の哲学」の「道徳」で登場する「悪の類型」も「近代人の性格」を見抜いているわけで、近代をそれほど楽観的には思っていないと思う。'3)ヘーゲルは感覚と理性を現実の相では分けておらず、理性の中にも感性があって、若いマルクスが言うように、感覚を軽視したり、感覚のない合理性に傾斜した思想家ではなかったと思う。'4)質疑応答に「使用価値」を今日の「需要」に結び付けて考えて質問した例が、206ページと208ページにあって、思想史的には時代錯誤かもしれないが、今日的な視点では、なかなか面白いみかたで、もう少し真正面から議論しても良かったような気がする。入門書を期待する人にも、内容に或る程度以上通じた人にも、良書であるという意味で大成功だったと思う。